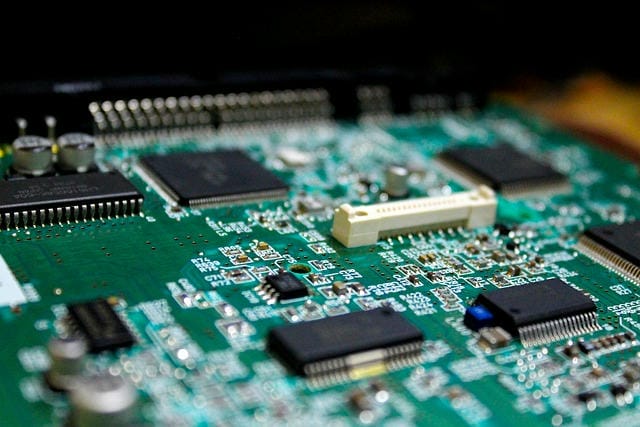DDoS攻撃の巧妙化と端末サーバー双方から考える多層防御の重要性
インターネットを利用する際に、見えない脅威として存在しているものに、ネットワークを使った攻撃が挙げられる。そのなかでも多くの被害を引き起こし続けている手法のひとつがDDoS攻撃である。分散型サービス妨害攻撃とも呼ばれ、特定のウェブサーバーやネットワーク機器などに向けて、大量のリクエストやデータを一度に送信し、システムやサービスを利用できなくしたり大幅な遅延を引き起こさせることが目的となっているのが特徴だ。仕組みを知ることで、自身の端末や運営するサービスを守る第一歩となる。DDoS攻撃が成立する仕組みは非常に巧妙である。
攻撃者はまず多数の端末を操作するために、インターネット上の個人や企業のパソコン、スマートフォン、ウェアラブル機器や家庭用ルータといったデジタル機器をウイルスやマルウェアに感染させる。攻撃者によって遠隔操作されたこれらの端末は「ボット」や「ゾンビ端末」などと呼ばれる。攻撃者は用意した大量のボット端末に指令を出し、対象とするサーバーやネットワーク機器へ一斉に通信を送る。その通信量がサーバーやシステムの処理能力を大きく上回ることで、正常なリクエストにも応答できなくなり、最悪の場合サービスが停止する事態に陥る。攻撃手法は年々多様化、複雑化しつつある。
ひとつは標準的なパターンとして、HTTPSやHTTPプロトコルなどウェブサービスが普段利用している通信を模倣し、大量のアクセスを装うというものがある。この場合、サーバーが本物の利用者からのアクセスと攻撃者のリクエストを識別するのは困難を極める。他にもDNSリクエストを増幅させる攻撃や、TCPやUDPといった異なるネットワーク層のプロトコルを狙った攻撃手法も多く報告されている。一回の攻撃で消費される帯域やデータ量も大規模化しており、一般的なウェブサーバーでは防御するのが難しい規模にまで到達している。DDoS攻撃を受けた場合の具体的な影響も深刻だ。
まず、利用者がウェブサイトやサービスにアクセスできなくなることで、企業や個人の信頼は著しく損なわれる。被害が長期化した場合、ウェブサイト経由の売上損失やブランドイメージの悪化も無視できない。更に、被害を最小限に留めようとすると追加的なセキュリティ対策が必要となり、コストがかさむ。各種通信サービスや基幹システムまで停止する事例も発生しており、社会インフラの安全性さえも脅かしかねないリスクといえる。攻撃の発信元となる端末側にも大きな課題が潜んでいる。
マルウェアやウイルスの感染経路としては、不正なリンクのクリックや、公式でないアプリケーションのインストール、古いバージョンのOSやソフトウェア利用などが挙げられる。一度感染した端末は、自身がボットネットの一部となって知らない間に他者への攻撃の加担者となる可能性が非常に高い。そのため端末利用者自身も、セキュリティソフトの導入やシステムの定期的なアップデート、不審なメールやアプリのインストールに注意することが重要だ。攻撃対象となったサーバー側でも、日常的な監視や抜本的な防御策が必要である。不審な通信の急増や、特定時間帯にアクセス数が急激に伸びた場合には、直ちに原因調査やフィルタリングの適用が求められる。
Webアプリケーションファイアウォールの導入、通信トラフィックの分散、外部ネットワークとの間にあるゲートウェイでの異常検知、自動遮断など、多層的な対策が欠かせない。第三者のサービスを利用した防御体制の強化や、万一の場合のための復旧計画といった事業継続のための準備も急務となっている。安全なインターネット利用を目指すためには、攻撃者から狙われる端末にも、攻撃を受けやすいサーバーにも、多面的な視点での自衛と予防措置が必要である。DDoS攻撃に関する脅威や事例は日々報告されているが、それぞれの利用者と事業者が正確な知識と不断の対策を講じることで、多くの被害は未然に防ぐことができる。これからも端末とサーバー防御の両面で意識を高め、巧妙化する脅威に対処し続ける姿勢が重要である。
DDoS攻撃は、インターネットを利用する際に見えない大きな脅威のひとつである。攻撃者はマルウェアやウイルスを用いて一般のパソコンやスマートフォン、IoT機器など多数の端末を遠隔操作し、「ボット」として一斉に標的サーバーやネットワーク機器へ莫大なリクエストやデータを送る。これによりシステムは過負荷となり、サービス停止や大幅な遅延が生じ、企業や個人の信頼失墜や経済的損失、ひいては社会インフラの安全性にも影響を及ぼす事態が発生する。攻撃手法は年々高度化しており、ウェブ通信を模倣するものからDNS増幅、様々なネットワーク層を狙ったものまで多岐にわたる。被害規模の拡大により、一般的なサーバーでは防御が困難なケースも珍しくない。
被害を防ぐためには、端末利用者自身がセキュリティソフトの導入やOS・アプリの更新、不審なリンクの回避など基本的な対策を徹底することが求められる。同時にサーバー管理側も、異常通信の監視・検知、トラフィック分散、ファイアウォール導入、迅速な原因調査など多層的な防御策を日常的に講じる必要がある。利用者と事業者双方が正しい知識と意識を持ち、継続的な対策によって巧妙化するDDoS攻撃の脅威に備える姿勢が大切だ。