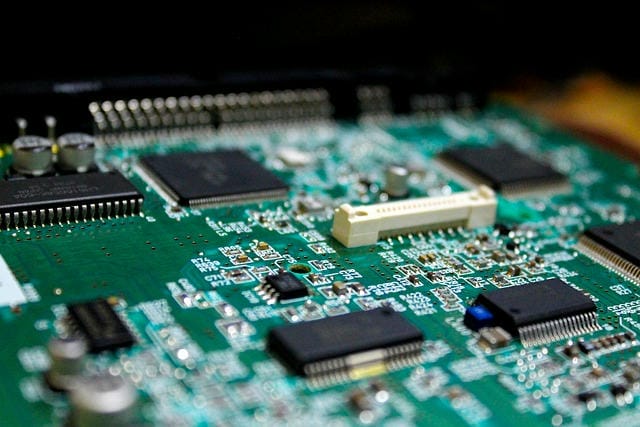DDoS攻撃がもたらす現実と日常機器も巻き込むネットワーク社会の脆弱性
膨大なトラフィックによって意図的にネットワークやサーバーを過負荷状態に陥らせ、正常なサービス提供を妨害する行為が社会問題となっている。このような妨害行為は、多くの端末を操ることで成立する。しかも、攻撃を実施する側は一つや数台の端末だけによる単純な妨害では精度も規模も望めないため、多数の端末を集中的かつ同時に用い、大規模にデータ要求やリクエストを送信する仕組みを活用している。まず、攻撃に用いられる端末には特殊な機器が必要かと思われがちだが、実際にはインターネットに接続されている一般的なパソコンやスマートフォン、場合によってはインターネット接続機能を持つ家電が利用されることが多い。悪意ある第三者は、脆弱性を突くことで不特定多数の端末へ不正プログラムを送り込み、それらをリモートで操作する状況を作り上げる。
そして、こうして集めた大量の端末から指示を一斉に発信し、ある特定のサーバーを標的とした大規模なリクエスト攻撃を仕掛けることで、狙ったサーバーが本来の業務処理をできない環境を人為的に作り出すことができる。標的となるサーバーは最も大きな被害を受ける。サーバーは本来、利用者のリクエストに応じてデータをやり取りし、Webページの表示やメールの送受信、業務システムへの接続などを管理する役割を持っている。ところが悪意のある攻撃トラフィックが通常の何十倍、何百倍にも膨れ上がってサーバーに到達すると、システムの処理能力を圧倒的に超えてしまう。サーバーはリクエストへの応答ができず、コンピューター内部で動作しているさまざまなソフトウェアやネットワークインターフェースそのものも停止状態や再起動状態に陥ってしまう。
その結果、本来サーバーのサービスを利用したかった一般利用者はアクセスできなくなり、企業にとっては大きな信用失墜や重大な経済的損害が発生する。この種の攻撃は高度かつ複雑化しており、ひと昔前の単純な大量トラフィック集中型のみならず、多彩な技術が駆使されている。例えば、本来なら正常なリクエストとしてサーバーに認識されるパケット構造を用いて攻撃することで、サーバーの防御壁を突破する手法もある。また、攻撃を複数の波状に分けて持続的に実施するケースや、異なるサーバーを同時に狙う広域戦術型の手段も登場している。日常生活の中にあるインターネット接続機器も攻撃に加担してしまう可能性があり、ネットワークの管理者がどれほど注意していても、全ての端末を適切に防御することはますます難しくなっている。
特に個人や小規模なシステム運用者は、端末のセキュリティアップデートや認証設定、不自然な通信記録の検知など地道な対策が欠かせない。攻撃側が利用する端末は、被害者であると同時に加害者にもなり得る。設置済みのネットワークカメラやルーター、ゲーム機器など、無自覚のまま攻撃の一端を担う事例が後を絶たないため、定期的なソフトウェアの更新や予期せぬ外部通信の遮断など、多重の守りを構築することが求められる。サーバー側でも、大容量のトラフィックを受け止めきれる強固なインフラ構築のみならず、異常なリクエストを短時間に検知し切断する自動監視システムが導入されつつある。さらに、複数拠点へのデータ転送分散や、あらかじめ攻撃を予見して通信制限を設ける策など、さまざまな防御策が模索されている。
しかし、こうしたセキュリティ対策に莫大なコストと知識が伴うため、世の中全体のネットワークを均一に守り切るというのは困難を極める。この問題がもたらすリスクはインターネット社会そのものへの信頼崩壊にもつながる。サーバーを経由して行われるインフラサービス、行政手続き、電子商取引などが一時的に使えなくなるだけではなく、長期的に見て経済活動や情報交換が阻害される懸念がある。日本国内外で発生した大規模な障害事例では、緊急対応や復旧作業に高額な費用が計上され、流通や利用者の生活にも大きな支障が出たと報告されている。多様化し複雑化するネットワーク環境において、安全性や信頼性の維持は今後ますます重要である。
そのためにも全ての端末を正しく管理し、攻撃手法の変化に応じて対策の見直し・強化を進めることが求められる。一つ一つの端末やサーバーの安全意識を高めつつ、ネットワーク社会全体として連携した取り組みが不可欠であるといえる。近年、ネットワークやサーバーを意図的に過負荷状態へと追い込み、正常なサービスを妨害する攻撃が深刻な社会問題となっている。このような攻撃は、単一の端末ではなく、インターネットに接続された多くの一般的なパソコンやスマートフォン、さらには家電製品までが悪意のあるプログラムによって遠隔操作され、大規模なリクエストを一斉に送ることで実行される。標的とされたサーバーは通常の処理能力を超えるトラフィックに対応できず、停止や再起動に追い込まれるため、企業や利用者にとって大きな被害となる。
攻撃手法の高度化により、従来のシンプルなトラフィック集中型だけでなく、正規の通信を装ったものや、波状的・分散的な攻撃も増加している。そのため、一般家庭のネットワーク機器さえ攻撃に利用されるリスクがある。対策としては、個々の端末のセキュリティ対策や定期的なソフトウェア更新、サーバー側での自動監視システムや通信分散などが模索されているが、コストや知識面で限界があるため、社会全体で連携した取り組みが不可欠である。インターネット社会の信頼性を維持するため、全ての端末とサーバーの管理を徹底し、不断の対策強化が求められる。